戸籍や古い記録を読み解くとき、「○○元年生まれ」「○○8年没」など、和暦で書かれていることが多くあります。
でも実際には、「そのとき何歳だったのか?」を知るのは、なかなか大変ですよね。
そこで、和暦の「生年月日」と「出来事の日付」を入力すると、年齢が自動で表示されるツールをつくりました。
江戸時代の初期である慶長(1596年)から令和までの和暦に対応しています
目次
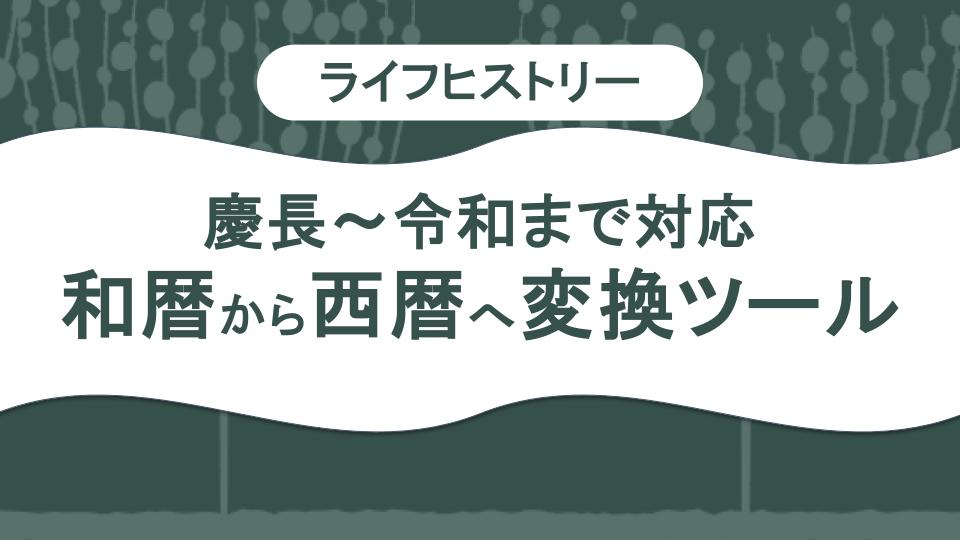
戸籍や古い記録を読み解くとき、「○○元年生まれ」「○○8年没」など、和暦で書かれていることが多くあります。
でも実際には、「そのとき何歳だったのか?」を知るのは、なかなか大変ですよね。
そこで、和暦の「生年月日」と「出来事の日付」を入力すると、年齢が自動で表示されるツールをつくりました。
江戸時代の初期である慶長(1596年)から令和までの和暦に対応しています