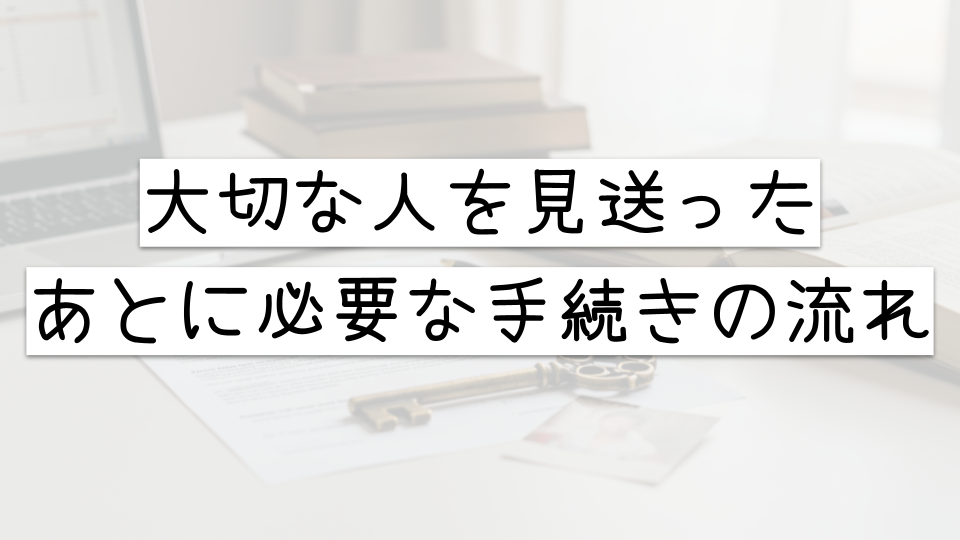ご家族を見送った後、気持ちの整理がつかないまま、いろいろな手続きを進めなければならない場面に直面する方は多いと思います。
市役所への届出や、年金・保険の停止、銀行口座やクレジットカードの手続き、そして相続の準備…。
「何から始めればいいの?」「どこにいつまでに申請すればいいの?」と不安になるのは当然です。
ご家族を見送ったあとに必要になる手続きには、大きく分けて「行政機関や民間での届出や解約」と「財産を引き継ぐための相続手続き」があります。
この記事では以下の2つを参考にしています
浜松市が発行している「おくやみガイド」(死亡届提出後のご遺族の手続き)(2024年3月版)
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/siminkj/okuyami_guide/index.html
政府広報オンライン「知っておきたい相続の基本」【基礎編】
https://www.gov-online.go.jp/article/202403/entry-5848.html
「死亡届の提出」にはじまり、「財産の引き継ぎ」へと進むまでの流れを
- どんな手続きがあるのか
- いつまでに対応する必要があるのか
が一目でわかるよう、わかりやすくまとめています。
大まかな2つの流れ
大切な方を見送った後の手続きは、大きく分けて以下の2ステップに整理できます。
- 行政機関や民間機関等への各種手続き
- 亡くなったことの届け出
- 死亡届(戸籍)の提出
- 死亡届提出の証明書発行
- 葬式・火葬等
- 亡くなったことに関する手続き
- 行政機関への手続き
- 年金に関する手続き
- 民間等への手続き
- 亡くなったことの届け出
- 財産を引き継ぐための相続手続き
- 遺産分割協議前
- 個人の資産に関する契約書等の調査(遺言書を含む)
- 相続人の調査(戸籍)
- 金融資産・動産の調査
- 不動産の調査
- 相続放棄・限定承認
- 遺産分割協議
- 遺産分割協議後
- 金融資産・動産の名義変更等
- 不動産登記
- 相続税の申告
- 遺産分割協議前
この2つのフェーズごとに、何をすればよいかを確認していきましょう。
1.行政機関や民間機関等への各種手続き
①「死亡届の提出」と火葬の手続き
ご家族を見送ったあと、まず行うことのひとつが「死亡届」の提出です。
これは法律上の届け出で、亡くなられた日から原則7日以内に、届出資格のある方(親族や同居人、後見人など)が市区町村役場へ届け出る必要があります。
実際には、葬儀会社の方が「死亡診断書」や「火葬許可申請書」などをまとめて提出してくれるケースも多いため、葬儀の段取りと一緒に進むことがほとんどです。
死亡届を提出すると、「火葬許可証」が交付されるほか、さまざまな証明書(戸籍謄本・住民票除票など)が発行できるようになります。
②死亡届を出したあとの「証明書の発行」について
相続や年金、保険の手続きでは、故人が亡くなったことを証明する書類が必要になります。ただし、届出後すぐには発行できない場合もあるので、以下の目安を参考にしてください。
≪証明書発行までの目安≫
※死亡届を提出した場所によって、戸籍や住民票が発行できるようになる日数が異なります。
※年末年始の休暇とゴールデンウィーク等の連休前後の場合は日数が異なります
▼戸籍事項証明書(戸籍謄本・除籍謄本など)
| 届出場所 | 発行までの目安 |
|---|---|
| 本籍地の役所に提出 | 届出の5日後(開庁日換算)以降に取得可能。 |
| 本籍地以外に提出 | 届出の内容が戸籍に記載されるまで時間がかかるためさらに日数がかかる 余裕をもって確認が必要。詳しくは本清吉の市区町村に問い合わせしましょう |
▼住民票の写し
| 住所地 | 発行までの目安 |
|---|---|
| 浜松市内で届出した場合 | 届出の2日後(開庁日換算)以降に取得可能 |
| 浜松市外で届出した場合 | こちらも上記の戸籍事項証明書と同様に住所地以外だと時間がかかる |
≪証明書を取得するには?(浜松市の場合)≫
戸籍事項証明書の取得方法
- 請求先
- 故人の本籍がある市区町村役場
- 請求できる人
- 亡くなられたた方の配偶者
- 同じ戸籍に名前がある方
- 直系の親族(例:親・子)
- 手数料
- 戸籍全部/個人事項証明書 1 通 450 円
- 除籍全部/個人事項証明書、除籍謄/抄本、改製原戸籍謄/抄本 1 通 750 円
- 持ち物
- 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、保険証と年金手帳 等)
- 続柄の確認ができるもの(浜松市内の戸籍で確認できる場合は不要)
住民票の写し(除票)
- 請求先
- 住所をおいていた区役所
- 請求できる人
- 亡くなられた後の手続きを行うにあたって、提出先から求められた方
- 手数料
- 1 通 350 円
- 持ち物
- 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、保険証と年金手帳 等)
- 疎明資料(続柄の分かる戸籍や、保険証書等、お手続きによって必要なものが異なる)※事前に各区区民生活課までお問い合わせが必要
③行政機関での主な手続き一覧
ご家族を見送ったあと、市役所や区役所、支所などで行う手続きにはさまざまなものがあります。
ここでは、浜松市の「おくやみガイド」に沿って、役所で行う主な手続きを、該当する方・手続き内容・手続き期限ごとに一覧でご紹介します。それぞれの担当窓口は各行政機関にお問い合わせください。
🏠 住民関係
| 確認項目 | 手続き | 期限 |
|---|---|---|
| □世帯主であった | □世帯主変更の手続き | ◎ |
| □市民カード(印鑑登録証)を所持していた | □市民カードの返納の手続き | |
| □パスポートを所持していた | □パスポートの返納 |
💰 年金
| 確認項目 | 手続き | 期限 |
|---|---|---|
| □国民年金のみに加入していた | □国民年金の手続き | △ |
| □遺族基礎年金・寡婦年金・障害基礎年金のみ受給していた | □未支給年金の請求 | △ |
| □老齢基礎年金・厚生年金を受給して いる | ※市役所以外の主な手続き参照 |
🧓 介護
| 確認項目 | 手続き | 期限 |
|---|---|---|
| □65 歳以上の方または介護認定を受けていた | □介護保険資格喪失届の提出 (介護保険被保険者証の返還) □相続人代表者に関する届の提出 □介護保険負担割合証の返還 □介護保険負担限度額認定証の返還 □社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証の返還 | ◎ |
🏥 健康保険
| 確認項目 | 手続き | 期限 |
|---|---|---|
| □国民健康保険に加入していた □国民健康保険に加入している世帯の世帯主であった | □国民健康保険被保険者証の返納 □葬祭費支給申請の提出 □相続人代表者に関する届の提出 | 一部△ |
| □後期高齢者医療保険に加入していた | □後期高齢者医療被保険者証の返納 □葬祭費支給申請の提出 □相続人代表者に関する届の提出 | 一部△ |
| □上記以外の各種健康保険に加入して いる | ※市役所以外の主な手続き参照 |
💸 税金
| 確認項目 | 手続き | 期限 |
|---|---|---|
| □浜松市税を口座振替で納税していた | □市税の口座振替停止の手続き | |
| □個人市民税・県民税の納税義務者であ った | □相続人代表者指定届の提出 □納付書の再発行 | |
| □固定資産税の納税義務者であった | □固定資産税の相続人代表者届書兼 現所有者申告書 | △ |
| □原動機付自転車、小型特殊自動車を所 有していた | □原動機付自転車、小型特殊自動車 の名義変更、廃車などの手続き | 〇 |
| 以下を所有していた □普通自動車 □軽自動二輪車 □二輪小型自動車 □軽自動四輪車 □ボートトレーラー | ※市役所以外の主な手続き参照 | |
| □国税関係 | ※市役所以外の主な手続き参照 |
♿ 障がい福祉
| 確認項目 | 手続き | 期限 |
|---|---|---|
| 下記のいずれかを所持していた □身体障害者手帳 □療育手帳 □精神障害者保健福祉手帳 □自立支援医療受給者証(精神通院) □自立支援医療受給者証(更生医療) | □身体障害者手帳の返還 □療育手帳の返還 □精神障害者保健福祉手帳の返還 □自立支援医療受給者証(精神通院)の返還 □自立支援医療受給者証(更生医療)の返還 | × |
| 下記のいずれかを利用していた □重度心身障害者医療費助成 □精神障害者医療費助成 | □重度心身障害者医療費助成資格喪失の手続き □重度心身障害者医療費助成支払金振込口座の変更手続き □精神障害者医療費助成申請の手続き | 一部△ |
| □特別児童扶養手当を受給していた □特別児童扶養手当の対象児童であった | □特別児童扶養手当の手続き、申請 | 一部◎ or△ |
| 下記のいずれかの手当を受給していた □特別障害者手当 □障害児福祉手当 □経過的福祉手当 | □特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当の手続き | 一部◎ or△ |
| □心身障害者扶養共済に加入している | □心身障害者扶養共済の年金受給の給付請求 □心身障害者扶養共済の障がい者死亡による弔慰金の給付請求 □心身障害者扶養共済年金受給者の死亡の届出 |
👶 児童福祉
| 確認項目 | 手続き | 期限 |
|---|---|---|
| □未成年の子の父または母が亡くなった 下記のいずれかを利用していた □児童手当 □児童扶養手当 □遺児・交通遺児手当 □ひとり親家庭等医療費助成 □母子父子寡婦福祉資金貸付金 | □児童手当の申請、未支払請求 □児童扶養手当の申請、手続き □遺児・交通遺児手当の申請、手続き □ひとり親家庭等医療費助成の手続き、申請 □母子父子寡婦福祉資金貸付金の手続き | 一部〇 or◎ |
🤝 その他福祉
| 確認項目 | 手続き | 期限 |
|---|---|---|
| □小児慢性特定疾病医療費受給者証を所持していた | □小児慢性特定疾病医療費受給者証の返還 | |
| □亡くなった方が被爆者健康手帳の交付を受けていた | □被爆者葬祭料の支給申請 | △ |
| 下記のいずれかを所持していた □特定医療費(指定難病)受給者証 □静岡県特定疾患医療受給者証 | □特定医療費(指定難病)受給者証の返還 □静岡県特定疾患医療受給者証の返還 | |
| ひとり暮らし高齢者の方で 下記を利用していた □配食サービスを利用していた □緊急通報システム装置の利用していた | □ひとり暮らし高齢者等配食サービス事業の廃止手続き □ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業の廃止手続き | |
| □軽度生活援助員派遣事業を利用してい た | □軽度生活援助員派遣事業の廃止手続き | |
| □外国人高齢者福祉手当を受給していた | □外国人高齢者福祉手当受給者資格 変更届出書等の提出 | |
| □徘徊高齢者早期発見事業(オレンジシール交付)に登録していた | □浜松市徘徊高齢者早期発見事業 (オレンジシール交付)登録廃止届の提出 | |
| □ゆずりあい駐車場利用証を利用していた | □ゆずりあい駐車場利用証の返却 |
🚰 水道・下水道
| 確認項目 | 手続き | 期限 |
|---|---|---|
| □水道・下水道を使用していた | □水道・下水道の使用者変更 | |
| □下水道受益者負担金を完納していない | □下水道受益者負担金の受益者変更 | |
| □井戸水を使用していた | □井戸使用世帯人員の変更 | |
| □給水装置所有者であった | □給水装置所有者変更の届出 | |
| □浄化槽の使用者又は管理者であった | □浄化槽管理者の変更 | 〇 |
🧾 暮らし
| 確認項目 | 手続き | 期限 |
|---|---|---|
| □市営墓所を利用している | □墓所利用権承継申請 □納骨届の提出 | |
| □浜松市納骨堂の生前登録をしている | □永年納骨依頼届の提出 | |
| □犬を飼っていた | □犬の飼い主変更手続き | 〇 |
| □森林の土地を所有していた | □森林の土地の所有者届出 | △ |
| □農地の権利を所有していた | □農地を相続した旨の届出 | △ |
| □市営住宅に入居していた | ※市役所以外の主な手続き参照 | |
| □遺言書を作成していた | ※市役所以外の主な手続き参照 | |
| □運転免許証を所持していた | ※市役所以外の主な手続き参照 | |
| □在留カードを所持していた | ※市役所以外の主な手続き参照 |
④市役所・区役所・支所以外での主な手続き一覧
お別れの後の手続きは、市役所・区役所以外でも数多く発生します。
特に金融機関や保険、携帯電話、公共料金など、故人名義で契約していたものは名義変更や解約、給付申請などが必要です。
ここでは、浜松市の「おくやみガイド」に掲載されている市役所以外の主な手続きを、カテゴリごとに分かりやすくまとめました。
🏦金融・保険・契約関係
| 対象 | 主な手続き | 問い合わせ先 |
|---|---|---|
| □生命保険等 | □死亡保険金の請求 □入院給付金の請求 等 | ・加入していた生命保険会社または代理店 |
| □各種健康保険 | □保険証の返納 等 | ・加入していた健康保険の組合や団体 等 |
| □預貯金口座等 | □口座凍結の解除 | ・各金融機関 等 |
| □株式等 | □名義変更 | ・証券会社 等 |
| □国債 | □記名変更 □償還金受領 | ・償還金支払場所または証券保管証書に記載の郵便局 |
📱生活インフラ・通信関係の手続き
| 対象 | 手続き内容 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|
| □クレジットカード | □解約・支払い確認 | 各カード会社 |
| □固定電話・携帯電話 | □解約・名義変更 | 各キャリア(docomo、au、SoftBankなど) |
| □インターネット | □解約・名義変更 | 契約中のプロバイダー |
| □NHK受信料 | □解約・名義変更 | NHKカスタマーサービス |
| □電気・ガス・水道 | □解約・名義変更 | 各地域の電力・ガス・水道会社 |
| □ケーブルテレビ | □解約・名義変更 | 各CATV会社 |
🚗車・運転免許などの手続き
| 対象 | 手続き内容 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|
| □自動車(普通車) | □廃車・名義変更 | 最寄りの自動車検査登録事務所など |
| □軽自二輪車 (125cc を超え 250cc 以下) □二輪小型自動車 (250cc を超えるもの) | □廃車・名義変更 | 最寄りの軽自動車検査協会など |
| □運転免許証 | □返納 | 最寄りの警察署または運転免許センター |
🏠法務局・税務署・家庭裁判所に関する手続き
| 対象 | 手続き内容 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|
| □不動産登記関係 | □相続登記(名義変更) | 最寄りの法務局 |
| □国税関係(相続税など) | □各種申告・相談 | 最寄りの税務署 |
| □遺言書がある場合 | □検認・開封 | 最寄りの静岡家庭裁判所 |
| □相続放棄 | □相続放棄の申立て | 同上 |
🧾年金関連の手続き
| 対象 | 手続き内容 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|
| □老齢基礎年金・厚生年金 | □未支給年金の請求 | 最寄りの年金事務所 |
🌐在留カード・市営住宅等
| 対象 | 手続き内容 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|
| □在留カード・特別永住者証 | □返納 | 最寄りの出入国在留管理局など |
| □市営住宅 | □入居者・同居人の変更手続き | 最寄りの市営住宅管理センターなど |
2.財産を引き継ぐための「相続」手続き
ご家族を見送ったあとに必要になる手続きには、大きく分けて「行政機関や民間での届出や解約」と「財産を引き継ぐための相続手続き」があります。
なかでも相続は、亡くなったその時点から法的にスタートしている手続きです。相続とは、亡くなった方の財産や義務を引き継ぐことであり、身近な人が亡くなった際には、誰にでも関係する可能性があります。
日常的に経験することではないからこそ、基本的な流れや制度を知っておくことで、いざというときに冷静に対応することができます。
ここでは、相続の全体像と、押さえておきたいポイントをわかりやすく整理していきます。
⓪:相続とは
相続とは、亡くなった方の財産や権利・義務を、残されたご家族が引き継ぐことをいいます。
相続においては、「誰が・何を・どう分けるか」という点について、法律(民法)で基本的なルールが定められています。
相続には大きく分けて、以下の2つの方法があります:
- 法定相続:民法で定められた相続人・相続分に基づいて引き継ぐ
- 遺言相続:遺言書の内容に従って引き継ぐ(原則として遺言が優先)
遺言書がある場合は基本的にその内容に沿って財産が分けられますが、遺言書がない場合や、書かれていない財産がある場合には、法定相続に基づき、相続人全員による話し合い(遺産分割協議)によって、誰がどの財産をどの割合で受け取るのかを決めていくことになります。
また相続財産には、現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
そして、財産の内容や相続の方法によっては、相続放棄や相続税申告など、一定の期限内に手続きをしなければならないものもあります
①:遺産分割協議の前にやること
相続を進めるにあたって、まず必要なのが「相続人や財産の状況をしっかり把握すること」です。
相続では亡くなった人を「被相続人」と呼びます。財産を引き継ぐのは民法で定めた「法定相続人」と、亡くなった人が遺言書で財産の受け取りを指定した「受遺者」です。
相続の手続きを進めるうえで、まず必要なのは、「相続人」と「受遺者」を正確に把握することです。
遺言書がない場合でも、また遺言書があっても、相続人の調査は基本となる大切な作業です。
なぜなら、不動産の名義変更や預貯金の手続きなどでは、相続人全員の同意が必要になるからです。
🧾 遺言書の有無を確認する(遺言相続があるかどうか)
遺言とは、ご自身が旅立ったあとに、大切な財産を「どのように・誰に・どれだけ」引き継いでほしいか、その意思を伝えるためのものです。
亡くなられた方が生前に遺言書を残していた場合、その内容が基本的には最優先されます。これを「遺言相続」と呼びます。
遺言書があることで、次のようなことが可能になります:
- 法律上は相続人にあたらない方(内縁の方やお世話になった知人・団体など)にも財産を遺せる
- 特定の財産(たとえば家や土地)を、特定の相手に引き継がせることができる
- 「誰に・何を」明確にできるので、相続人同士のトラブルを防ぐ効果も
- 想いを文章に残すことで、遺された人たちにメッセージを届けられる
一般的に多く用いられる遺言の方法としては、遺言者自らが手書きで書く「自筆証書遺言」と、公証人(国の公務である公証作用を担う実質的な公務員)が遺言者から聞いた遺言の趣旨を記載し、公正証書として作成する「公正証書遺言」の2種類があります。
自筆証書遺言が残されていた場合
自筆証書遺言は、ご本人がご自身の手で書いて残す遺言のことです。基本的には、全文・日付・氏名をすべてご本人の手書きで書き、押印する必要があります。
財産目録(どんな財産があるかをまとめた一覧表)については、パソコンや代筆で作ってもかまいませんが、その場合もすべてのページに署名と押印が必要です。
自筆証書遺言は、法務局で安全に保管できます!
大切な想いを手書きで綴った「自筆証書遺言」。
でも、それを自宅に置いたままにしておくと火災や紛失、知られずに放置される…といった不安もあるかもしれません。
そんなときに安心なのが、「自筆証書遺言書保管制度」です。この制度は、2020年7月にスタートし、ご本人が書いた遺言書を法務局が預かってくれる仕組みです。遺言がちゃんと遺され、受け取る人に確実に届くように支えてくれます。
公正証書遺言が残されていた場合
「きちんと間違いなく、自分の想いを残したい」
そんな方に選ばれているのが、公正証書遺言という方法です。
公正証書遺言は、公証役場等で2人以上の証人の立会いの下、遺言者が遺言の趣旨を公証人に述べて、公証人がその内容を記載して作成する遺言書です。
自分で書く自筆証書遺言と比べ、要件を満たしていないなどの理由で無効になるリスクが少なくなります。なお、遺言書の原本は、公証役場で保管され、家庭裁判所の検認は不要です。
この「公正証書遺言」が作成されていたかどうかを、あとから公的に調べる方法があります。
Q1. 亡くなった方について、公正証書遺言が作成されているかどうかを調べることができますか?
出典:日本公証人連合会HP(https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02)
- 公正証書遺言の検索システム
平成元年以降に作成された公正証書遺言については、日本公証人連合会において、遺言情報管理システムを構築し、全国の公証役場で作成した遺言公正証書の情報(作成公証役場名、公証人名、遺言者名、作成年月日等)を管理しております。全国の公証役場において、このシステムで遺言公正証書の有無および保管公証役場を検索することができますので、お近くの公証役場にお申し出ください。遺言検索の申出は、無料です。- 検索の方法および必要書類等
遺言検索の申出は、秘密保持のため、相続人等の利害関係人のみが公証役場(公証人)に対してすることができます。申出の際の必要書類は、①遺言者が死亡した事実を証明する書類(除籍謄本等)、②遺言者の相続人であることを証明する戸籍謄本、③申出人の本人確認の書類(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付き公的身分証明書または実印および印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの))です。
なお、遺言者が亡くなる前は、遺言検索の申出は遺言者本人に限られています
👨👩👧 戸籍上の相続人を確定する(戸籍調査)
相続の手続きを進めるうえで、大切なステップが、相続人の確定です
上記では「遺言書を確認すること」をまとめましたが、今回は「相続人の調査・確定」についてです。
相続人を調べるためには、亡くなられた方(被相続人)の戸籍をたどる必要があります。
複数の市区町村役場への請求が必要となり、ある程度の期間がかかります。
具体的には、以下のような戸籍謄本などを集めます:
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍・除籍・原戸籍
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 必要に応じて、被相続人と相続人とのつながりを証明する戸籍
「法定相続情報証明制度」で手続きを簡素化できます
この戸籍調査が終わったら、ぜひ活用したいのが「法定相続情報証明制度」(2017年スタート)です。
集めた戸籍一式と、相続関係の一覧図を法務局に提出すると、法務局がその内容を確認し、「相続関係を証明する書類(一覧図)」を無料で発行してくれます。
この一覧図があれば、不動産の名義変更、預貯金の解約、保険の請求など、それぞれの手続きで毎回戸籍の束を提出する必要がなくなります。
相続人の種類と順序を整理する
戸籍の調査が終わったら、集めた情報をもとに「誰が相続人になるのか」を整理していきます。
民法では相続できる人(相続人になれる人)の範囲を定めており、これを「法定相続人」といいます。
法定相続人にあたるのは、亡くなった方の配偶者、そして一定の血縁関係にある親族(いわゆる「血族相続人」)です。具体的には、子どもや父母、兄弟姉妹などが該当します。
子どもには、実子のほかに養子や、法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子も含まれます。
また、胎児についても、出生すれば相続人となることが予定されているため、死産でない限り、相続人として扱われます。このように、法定相続人の範囲は、血縁関係や法律上のつながりによって広く定められており、それぞれのケースに応じた判断が求められます。
🪜 相続人の範囲と順位とは?
民法では、相続人になる「順位」が決められています。
| 順位 | 相続人の範囲 | 補足 |
|---|---|---|
| 第1順位 | 子(直系卑属)、孫、ひ孫など | 子がいない場合は孫が代襲相続 |
| 第2順位 | 父母、祖父母など(直系尊属) | 第1順位がいない場合に限る |
| 第3順位 | 兄弟姉妹、その子(甥・姪) | 第1・2順位がいない場合に限る |
※配偶者は常に相続人になりますが、順位のある血族と組み合わせて相続人になります。
👥 代襲相続とは?
本来相続人となる人(たとえば子ども)がすでに亡くなっていた場合、その子ども(つまり孫)が代わって相続人になる仕組みを「代襲相続」といいます。
兄弟姉妹が亡くなっていた場合にも、その子(甥・姪)が代襲相続人になります。
📊 相続分とは?
相続分とは、相続人が「どれだけの割合で財産を引き継ぐのか」を示すものです。
たとえば相続人が複数いる場合、亡くなった方の財産は相続人全員の共有という形になります。その上で、「それぞれが何割ずつ持っているのか(=持分)」を定めるのが相続分です。
相続分には「指定相続分」と「法定相続分」があります。
●指定相続分
亡くなった方が遺言で財産の分け方を指定していた場合、基本的にはその内容が優先されます。
これを「指定相続分」といい、法定相続分よりも強い効力を持ちます。
●法定相続分
遺言書がない場合や、遺言に書かれていない財産については、民法で定められた割合(=法定相続分)が目安となります。この法定相続分は、あくまで相続人同士で遺産分割の合意ができなかった場合などに使われるルールで、相続人全員の合意があれば、違う割合で分けても問題ありません。
以下は、法定相続分の一例です。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の取り分 | その他の相続人の取り分 |
|---|---|---|
| 配偶者のみ | 全部 | ー |
| 配偶者と子ども | 1/2 | 子ども全体で1/2を分ける |
| 配偶者と親 | 2/3 | 親全体で1/3を分ける |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹全体で1/4を分ける |
なお、相続人全員が合意すれば、この法定割合と異なる分け方も可能です(遺産分割協議)。
💰 財産の調査
相続手続きをスムーズに進めるためには、亡くなった方がどんな財産を持っていたのか、そしてそれがどこにあるのかを把握することがとても大切です。
相続財産の調査は、生前に話を聞いていたり、メモや一覧が残されていればスムーズに進みます。しかし、そういった準備がされていないまま急に旅立たれた場合、多くの相続人が「遺品の中から手がかりを探す」ところから始めなければなりません。
現状では、「被相続人のすべての財産を一括で調べる仕組み」は今のところ存在していません。そのため、相続人が一つひとつ手がかりをもとに調べていったり、専門家を活用したりすることになります。
相続財産とは、亡くなった方(被相続人)がその時点で所有していた「すべての財産」のことをいいます。
これはいわゆる「お金や土地」といった目に見えるものだけではなく、目に見えない権利や義務も含まれます。
🌱 代表的な「プラスの財産(資産)」
- 預貯金(銀行口座、定期預金など)
- 現金(タンス預金なども含む)
- 不動産(土地・建物)
- 株式や投資信託などの有価証券
- 自動車
- 貴金属や宝石、美術品
- 借地権や借家権
- ゴルフ会員権 など
⚠️ 見落としがちな「マイナスの財産(負債)」
- ローン(住宅ローン、車のローン)
- クレジットカードの未払金
- 借金(金融機関・個人からの借入)
- 保証人としての債務
- 未払いの医療費や税金など
これらも相続の対象です。プラスの財産と合わせて判断する必要があります。
預貯金なら、通帳などを手掛かりに金融機関に問い合わせを行います。固定資産税の納税通知書があれば、不動産がないか確認します。
相続財産の調査により、財産を整理することで、相続の選択や、分割協議、相続税の申告、金融機関など各種機関等への手続きなどスケジュールや作業負担を検討することができるようになります
相続の対象となる財産をまとめていきます。
②:相続の承認または放棄(3か月以内)
上記で考えてきたように遺産には資産(プラスの財産)だけでなく、借金などの負債(マイナスの財産)も含まれています。
そのため、相続人には亡くなった人(被相続人)の相続に際し、次の3つの選択肢が用意されています。
| 選択肢 | 内容 | 相続承認又は放棄をすべき機関 | 手続き |
|---|---|---|---|
| 単純承認 | 死亡した人(被相続人)の全ての財産を相続する。 | 下記の限定承認や相続放棄を行わなかったときは単純承認したとみなされる。(3か月経過で自動) | 特に必要なし |
| 限定承認 | 相続によって取得した資産(プラスの財産)の限度で負債(マイナスの財産)を引き継ぐ。 | 相続の開始があったことを知った日から3か月以内 | 相続人全員で家庭裁判所に申述する。 |
| 相続放棄 | 死亡した人(被相続人)の財産を全て相続しない。 | 相続の開始があったことを知った日から3か月以内 | 放棄する相続人が単独で家庭裁判所に申述する。 |
③:遺産分割協議を行う
遺産分割協議とは、相続人全員で集まり、「誰が」「どの財産を」「どんな割合で」受け継ぐのかを話し合って決める手続きです。
亡くなった人の遺産は、相続人全員の共有となります。この共有状態の遺産の分け方について話し合い、合意するのが遺産分割協議です。法定相続分や遺言の内容と異なる割合で相続分を決めることも可能です。
遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には、誰がどの財産をどのような割合で相続するのかを記載します。
🧾 協議内容を「遺産分割協議書」にまとめる
話し合いがまとまったら、内容を書面にまとめて「遺産分割協議書」を作成します。
法務省や専門家のWEBページ文例を参考にして頂き、形式、書き方の注意点を調べて頂きながらご自身で作成することもできます。
法務省民事局:登記申請手続のご案内(相続登記①/遺産分割協議編)
④:協議のあとの各種手続き
いよいよ実際の名義変更や申告など、「かたちに残る手続き」を進めていきます。
ここでは、主な3つの分野をご紹介します。
🏦 金融資産・動産の名義変更(預貯金・株式・保険・車など)
- 銀行・ゆうちょの預金口座
- 証券会社の株式や投資信託
- 生命保険や医療保険などの保険契約
- 自動車やバイクなどの登録財産 など
📌 手続きに必要な主な書類:
- 遺産分割協議書(原本+コピー)
- 被相続人の戸籍(出生から死亡までのすべて)
- 相続人全員の戸籍・印鑑登録証明書
- 本人確認書類(運転免許証など)
🏡 不動産、相続登記【2024年4月から義務化】
2024年4月以降、不動産の相続登記が法律で義務化されました。
- 相続したことを知った日から原則3年以内に名義を変更する必要がある
- 正当な理由なく怠った場合は、10万円以下の過料の適用対象となります
- 相続放棄をするには原則として相続発生を知った日から3カ月以内に手続きをする必要がある
📌 相続登記に必要な書類(一例):
- 遺産分割協議書
- 被相続人の戸籍と住民票の除票
- 相続人の戸籍・印鑑証明書
- 固定資産評価証明書(不動産の評価額を証明)
- 登記申請書(法務局で用意)
🧾 相続税の申告・納付【10か月以内】
相続が発生してから 10か月以内 に、相続税の申告と納税が必要になるケースがあります。
すべての人が対象というわけではなく、財産の総額が一定額(基礎控除)を超える場合に申告義務が生じます。
相続税についてわかりやすくまとめられている国税庁のホームページをご紹介します。
💡知っておくと便利な制度いろいろ
政府広報オンラインに掲載されていた、見落としがちな制度も紹介しておきます。
✅ 配偶者の「住まい」を守る2つの制度
残された配偶者が安心して暮らし続けられるように――
相続の場面では「住まい」に関する不安を和らげるための制度が整えられています。
ここでは、特に知っておきたい【配偶者居住権】と【配偶者短期居住権】についてご紹介します。
🕊️ 配偶者短期居住権とは?
亡くなった方(被相続人)が所有していた建物に、配偶者が一緒に住んでいた場合、すぐにその住まいを離れる必要はありません。
このとき適用されるのが「配偶者短期居住権」です。
- 遺産分割が終わるまで、無償でそのまま住み続けることができます。
- 万が一、遺産分割がすぐにまとまっても、少なくとも6か月間は居住が保障されます。
- たとえ配偶者が相続放棄をしていても、一定期間の居住は認められています。
これは、配偶者の生活環境を急に変えることのないように配慮された制度です。
📌 配偶者居住権と配偶者短期居住権の比較
| 種別 | 配偶者居住権 | 配偶者短期居住権 |
|---|---|---|
| 権利の取得 | 遺贈、遺産分割等により取得 | 相続開始時に無償で居住していたことなどにより発生 |
| 居住できる期間 | 遺贈、遺産分割等で設定された期間(設定されない場合は配偶者が死亡する時まで) | 相続開始時等から6か月 |
| 登記の可否 | 可(登記すれば第三者にも主張可能) | 不可(登記はできない) |
✅ 遺留分は“生活の保障”を守るための制度
遺言によって「すべての財産を◯◯さんにあげる」と指定されていても、直系の家族や配偶者には、生活のための取り分が一定割合で保障されています。
これは、亡くなった方(被相続人)が自由に財産を渡す権利と、遺された人たちの暮らしを守る権利とのバランスをとるために設けられた制度です。
🔢 誰に・どれだけ保障される?
遺留分を請求できる人は、限られています。
法定相続人のうち、以下のような方が対象です。
| 相続人の種類 | 遺留分の割合 |
|---|---|
| 配偶者・子ども・親(直系尊属) | 法定相続分の 1/2 |
| 親のみが相続人の場合 | 法定相続分の 1/3 |
| 兄弟姉妹 | 遺留分はありません |
💬 もし遺留分がもらえていなかったら…?
「遺言書の内容で、自分には何も残っていない」
そんなときには、遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)という方法があります。
これは、遺留分に足りない分の金銭を、贈与や遺贈を受けた相手に請求できる制度です。
📅 請求には期限があります
遺留分侵害額の請求は、ずっとできるわけではありません。
- 遺留分を侵害されたことを知ってから1年以内
- または、相続開始から10年以内
このどちらかを過ぎると、時効で請求できなくなるため注意が必要です。
✍補足
※本記事は、以下の公的資料をもとに一般的な情報として構成しております:
・浜松市「おくやみガイド」(2024年3月版)
・政府広報オンライン「知っておきたい相続の基本。大切な財産をスムーズに引き継ぐには?【基礎編】」なお、記事内容には十分配慮しておりますが、法改正や個別事情によって対応が異なる場合があります。
実際の手続きに際しては、必ず各自治体や専門家(行政書士・司法書士・税理士など)にご確認のうえ進めていただくようお願いいたします。