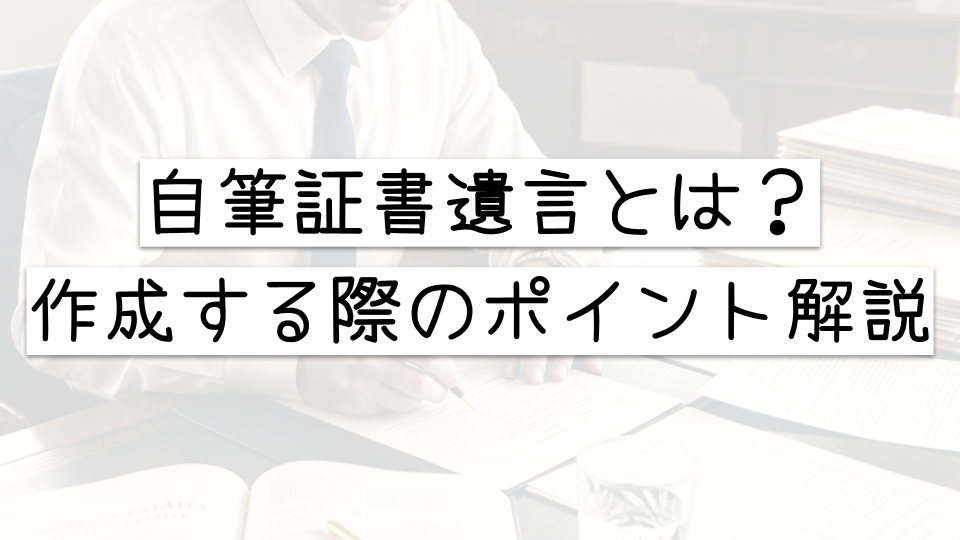遺言書と聞くと難しく感じるかもしれませんが、実はとても身近なものです。筆記用具さえあれば、いつでもどこでも書ける「自筆証書遺言」は、最も手軽な遺言方法です。
しかし、専門家の視点から見ると、ご自身だけで作成した遺言書が、かえって家族間のトラブルを招いてしまうケースも少なくありません。
この記事では、そんな自筆証書遺言の基本的な書き方から、安全な保管方法まで、分かりやすく解説します。
この記事の内容を参考に、まずはご自身で遺言書を作成してみましょう。もし疑問や不安があれば、専門家に相談するきっかけにしていただければ幸いです。
自筆証書遺言の基本を知ろう
遺言書にはいくつかの種類がありますが、最も手軽に作成できるのが「自筆証書遺言」です。
遺言書の代表的な作成方式を比較解説した記事はこちら!
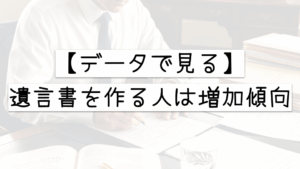
遺言者(遺言を書く人)が、遺言の全文、日付、氏名をすべて自分で手書きし、押印することで作成する遺言書のことです。
なぜ遺言書が必要なのか、ご自身の状況を振り返ってみましょう
遺言書は、あなたが亡くなった後、残された家族がスムーズに手続きを進め、あなたの意思を実現するための大切な手段です。
ご自身の状況を振り返り、「何を誰に、どのように遺したいか」を考えてみましょう。そうすることで、遺言書を作成するモチベーションが生まれてきます。
遺言書作りは、時間と労力がかかります。
最初の「一歩」を踏み出すのが大変だと感じるかもしれません。
ご希望があれば、お手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
遺言書が必要になる主なケース
- 夫婦の間に子どもがいない(遺言者の両親も亡くなっている時)
遺言書がない場合、配偶者だけでなく、亡くなった方の兄弟姉妹も相続人になります。配偶者に全財産を遺したいのであれば、遺言書が必要です。(兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言さえあれば全財産を配偶者に残すことが可能です)
- 再婚して、先妻の子どもと後妻がいる場合
血縁関係がないため感情的な対立が起こりやすく、トラブルに発展する可能性もあります。遺言書で相続分を明確にしておくことで、争いを防ぐことができます。
- 特定の財産を特定の人に遺したい
「自宅の土地・建物を長男に継がせたい」といった場合、遺言書がないと、不動産が相続人全員の共有状態になります。将来、売却や管理をする際に全員の同意が必要となり、手続きが複雑になります。
その他、身体に障害のある子に多く相続させたい、老後に面倒を見てくれた子に多く相続させたいなど、遺言者のそれぞれの家族関係の状況に応じて、財産を小計させたい場合には、遺言をしておく必要があります。
- 法定相続人以外の人に財産を遺したい
法定相続人ではない人(例:孫、内縁の配偶者、お嫁さん)や、お世話になった人、団体(お寺、NPO法人など)に財産を遺したい場合は、遺言書がなければ遺言者の意思は実現できません。
【必要なものリスト】作成前に揃えるべきもの
遺言書を書く前に、以下のものを揃えておきましょう。
- 筆記用具:鉛筆や消せるボールペンは使えません。インクが消えないボールペンや万年筆を選びましょう。
- 紙:決まった用紙はありません。しかし、法務局で遺言書を保管してもらう「自筆証書遺言書保管制度」を利用する際は、A4サイズの用紙を使う必要があります。スムーズな手続きのためにも、最初からA4サイズで作成することをおすすめします。
- 印鑑:押印は必須です。認印でも構いませんが、より確実にするために実印を使いましょう。
自筆証書遺言書保管制度に求められる様式等について
①用紙についてサイズ:A4サイズ
模様等:記載した文字が読みづらくなるような模様や彩色がないもの。一般的な罫線は問題ありません。
余白:必ず、最低限、上部5ミリメートル、下部10ミリメートル、左20ミリメートル、右5ミリメートルの余白をそれぞれ確保してください。余白が確保されていない場合や、余白に1文字でも何らかの文字等がはみ出してしまっている場合は、書き直していただかなければお預かりできません。
②片面のみに記載してください。用紙の両面に記載して作成された遺言書はお預かりできません。財産目録も同様です。
③各ページにページ番号を記載してください。ページ番号も必ず余白内に書いてください。例)1/2、2/2(総ページ数も分かるように記載してください。)
④複数ページある場合でも、ホチキス等で綴じないでください。スキャナで遺言書を読み取るため、全てのページをバラバラのまま提出いただきます(封筒も不要です。)。
また、以下の2つのリストを作成することが、遺言書作成において最も重要です。
- 相続人リスト:家族関係を整理し、誰が法定相続人になるのか正確に把握しましょう。この把握が不正確だと、遺言書に不備が生じ、トラブルの原因になります。
- 財産目録:不動産、預貯金、株式、借金など、ご自身のすべての財産を漏れなくリストアップします。特に借金などの負債も相続財産の一部となるため、正確に把握しておくことが大切です。
財産目録について 財産目録は、遺言書を正確に書くための重要なツールです。法改正により、この目録は手書きでなくてもよくなりました。不動産の登記事項証明書や預金通帳のコピーを添付することで、記載ミスや曖昧さを防ぐことができ、相続手続きをスムーズに進められます。
【絶対に外せないルール】有効な遺言書を書くための正しい書き方と注意点
自筆証書遺言を有効にするためには、法律で定められた厳格なルールを守る必要があります。
1. 遺言書の本文の書き方
- 全文「自筆」の原則と、唯一の例外
- 遺言書の本文、日付、氏名のすべてを、ご自身の手で書かなければなりません 。例えば、「老眼で見えづらいから」といって家族に代筆を頼んだり、一部でもワープロやパソコンで作成したりした場合は無効となります 。
- この原則には唯一の例外があります。2018年の法改正により、財産目録は自筆でなくてもよいと定められました 。パソコンで作成したり、通帳のコピーや不動産の登記事項証明書を添付することも可能です 。ただし、この場合でも、財産目録のすべてのページに署名と押印が必要です 。
- 「いつ書いたか?」を明確にする日付のルール
- 遺言書には、作成した年月日を正確に記載しなければなりません 。例えば、「〇〇年〇月吉日」のように特定の日が明記されていない日付は無効とされた最高裁判例が存在します 。
- 複数の遺言書が見つかった場合、新しい日付のものが古い日付のものに優先して効力を持つため、日付は遺言書の法的効力を決定する上で極めて重要な要素です 。
- 署名と押印の正しい方法
- 遺言書本文の末尾には、ご自身の氏名を自筆で書き、印鑑を押す必要があります 。押印は、実印が推奨されます。認印でも問題ありませんが、スタンプ印は避けてください。また、署名・押印が欠けていると無効になるため注意が必要です 。
- 加筆・訂正の厳格なルール
- 一度作成した遺言書の内容を訂正する場合、法律で定められた方法に従わなければ、その訂正部分は無効となります 。
- 正しい訂正方法は、遺言者が訂正箇所を二重線で抹消し、その変更した旨を書き加えて、その部分に署名押印するというものです 。
- このルールは複雑で間違いが起こりやすいため、変更・追加等がある場合には、書き直すことをおすすめします。
- 財産の渡し方、正しい書き方
- 誰に財産を遺すかによって、使う言葉が変わります。
- 相続人(配偶者、子どもなど)に財産を遺す場合は「相続させる」と書きます。
- 相続人以外の人(孫、甥、知人、団体など)に財産を遺す場合は「遺贈する」と書きます。
- 「任せる」「任せる」「渡す」といった曖昧な表現は、後のトラブルを避けるためにも使用しないでください
その他の大切な記載事項
- 「もしも」に備える 財産を遺したい人が、あなたより先に亡くなることも考えられます。万が一に備え、次に財産を渡したい人をあらかじめ決めておきましょう。これを書いておかないと、その部分の遺言が無効になり、家族で再び話し合う必要が出てきます。(こうした記載事項を「予備的遺言」と言われています)
- 借金についても記載する 借金も相続する財産の一部です。遺言書に明記しておくことが望ましいです。ただし、遺言書で借金を引き継ぐ人を指定しても、債権者は法律上の相続人全員に支払いを求めることができます。
- 家族へのメッセージ 法的な効力はありませんが、遺言書に「付言事項(ふげんじこう)」として、家族への感謝の気持ちや、遺言書を書いた理由などを書き残すことができます。これにより、家族の気持ちが和らいだり、相続争いを未然に防いだりする効果が期待できます。
財産を特定する方法
財産を正確に特定することで、トラブルを防ぎ、手続きをスムーズに進めることができます。
- 不動産 登記簿謄本に書かれている通り、正確な住所や番号をすべて記載します。複数の土地に分かれている場合でも、漏れがないようにしましょう。
- 預貯金 金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号を記載します。
- 株や証券 証券会社名、口座番号、銘柄、銘柄コードなどを記載します。
また、以下の点にも注意が必要です。
- 「その他一切の財産」の落とし穴 「その他一切の財産を○○に相続させる」という書き方だけでは、見落としやすい財産(共有の道路など)が対象外となり、意図しない人が取得する可能性があります。
- 未登記の建物 登記されていない建物でも、所在、構造、床面積などを記載し、漏れがないようにしましょう。
- 将来の財産 遺言書は、書いた後に取得した財産も対象にできます。「遺言者の有する一切の財産を○○に相続させる」と書いておけば、新しい財産も含まれることになります。
遺言書を安全に保管する方法
せっかく書いた遺言書も、紛失したり見つけてもらえなければ意味がありません。保管場所は非常に重要です。
| 保管方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 自宅で保管する | 費用がかからない | 家族に発見されないおそれがある 紛失、隠匿、改ざんのリスクがある |
| 法務局に預ける | 紛失・改ざんの心配がない 家庭裁判所の「検認」が不要 誰でも遺言書を閲覧できる | 申請手数料として3,900円がかかる 記載ルールを守る必要がある |
自宅で保管する場合の「良い場所」「悪い場所」
自筆証書遺言を自宅で保管する際は、保管場所によっては、せっかく書いた遺言書が無駄になってしまう可能性があります。
特に避けるべき場所は以下の2つです。
1. 貸金庫は避けたい
遺言書を貸金庫に保管するのはやめましょう。なぜなら、契約者が亡くなったことを金融機関が知ると、貸金庫は凍結されてしまうからです。
貸金庫を開けるには、原則として相続人全員の同意が必要です。もし、相続人の一人でも反対すれば、貸金庫を開けることができません。
自筆証書遺言の原本は一通しかありません。貸金庫の中に遺言書が閉じ込められてしまうと、遺言書の内容を確認できず、家庭裁判所の検認をはじめ、その後の相続手続きが一切進まなくなってしまいます。
2. 遺言書に不満を持つ可能性のある家族は避けたい
遺言書の内容を事前に知った家族が、その内容に不満を持った場合、「この遺言書さえなければ…」と破棄したり、隠したりするリスクがあります。特に自筆証書遺言は原本が1通しかないため、破棄されたり隠されたりすると、あなたの意思を実現できなくなってしまいます。
遺言書を預ける相手を決める際は、内容を見られることを前提に、「本当にこの人に預けて大丈夫か?」とよく考えてから判断しましょう。
遺言書のおすすめの保管場所
では、どこに保管するのが良いのでしょうか。おすすめの場所は以下の2つです。
- 法務局に預ける 2020年に始まった「自筆証書遺言書保管制度」を利用すれば、法務局があ遺言書を安全に保管してくれます。この制度を利用することで、遺言書が家庭裁判所の「検認」手続きを経る必要がなくなります。 また、法務局が遺言書を保管しているため、紛失や偽造、隠匿などの心配がありません。
- 遺言執行者 遺言執行者は、あなたの意思を実現してくれる人です。遺言書の内容に不満を持つ可能性のある家族以外に、信頼できる人(弁護士や司法書士、行政書士などの専門家)を指定しておくのも良い方法です。
- 遺言書に不満を持たない信頼できる家族 ご家族の状況により異なりますが、この保管場所が温かく安心できる保管場所ではないでしょうか。信頼できる家族であれば、遺言書の内容に限らず、これからの過ごし方など色々と時間をかけて話し合うことができます。あなたが亡くなった後もスムーズに手続きを進めることもできます。
【専門家への相談】どんなときに、誰に頼むべき?
遺言書作成は、ご自身の想いを形にする行為であり、複雑な財産や人間関係がある場合は、専門家への相談を検討することもオススメです。専門家は、単に法律的な形式をチェックするだけでなく、遺言者の人間関係や想いを汲み取り、将来的なトラブルが減らせるようにアドバイスをする役割も担います 。
専門家ごとの役割と相談費用の目安
| 専門家 | 主な専門分野 | 相談すべきケース |
| 弁護士 | 法律問題全般、紛争解決 | 相続人間に争いがある・予想される場合、複雑な法的アドバイスが必要な場合 |
| 司法書士 | 不動産登記、裁判所提出書類 | 遺産に不動産が多く、登記手続きまで見据えた遺言書を作成したい場合 |
| 行政書士 | 書類作成全般 | 遺言書の起案・作成支援のみを依頼したい場合、比較的シンプルな内容の場合 |
専門家を選ぶ際には、費用だけでなく、ご自身の状況と将来のトラブルリスクを考慮することが重要です。不動産が多い場合は司法書士、紛争の可能性が高い場合は弁護士、起案のみで費用を抑えたい場合は行政書士というように、それぞれの専門分野を理解し、最適なパートナーを選ぶことで、遺言書の作成も実りあるものになります。
まとめ
これまで見てきたように、自筆証書遺言は、ペンと紙さえあれば、あなたの想いを形にできる身近な方法です。
しかし、財産や家族関係が複雑な場合、書き方を間違えると、かえって家族間のトラブルを招いてしまう可能性があります
この記事で解説したポイントを参考に、まずはご自身で作成してみてはいかがでしょうか。もし、疑問や不安があれば、どうぞお気軽にご相談ください。