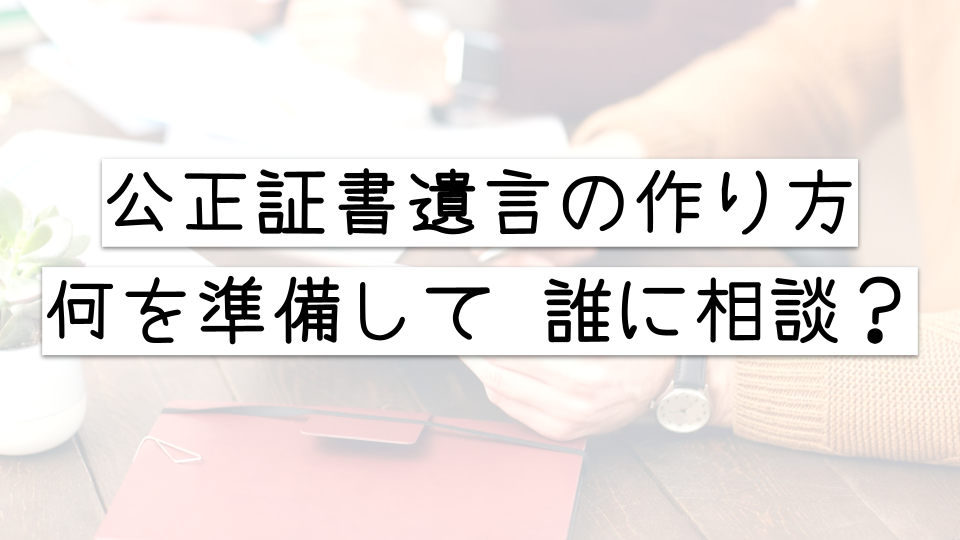公正証書遺言とは?メリットはある?デメリットは何?
公正証書遺言とは、法律の専門家である公証人が、遺言者の意思に基づいて作成する遺言書 です。遺言者が公証人や2人以上の証人の前で遺言内容を口頭で伝え、公証人がそれを文書にまとめ、作成されます。この形式の遺言書は、法律によって厳格な要件が定められており、その有効性と安全性が非常に高いことが特徴です。
遺言書の代表的なパターンの比較記事はこちら
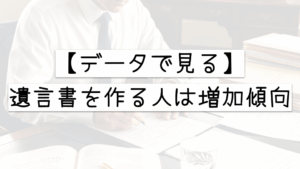
メリット
- 安全・確実性: 法律の専門家である公証人が作成するため、方式の不備で遺言が無効になる心配がありません。公証人は、遺言者の遺言能力や遺言内容の有効性を確認し、適切な助言を提供します。
- 確実な保管: 公正証書遺言の 原本は公証役場に厳重に保管され、遺言者の死亡まで他人の目に触れることはありません。これにより、紛失や偽造、改ざんのリスクがほぼなくなります。保管期間は、遺言者の死亡後50年、証書作成後140年または遺言者の生後170年間保存する取扱いになっています。
- 検認手続きが不要: 相続開始後、家庭裁判所での「検認(けんいん)」手続きが不要なため、速やかに相続手続きを進められます。
- 検索システム: 平成元年以降に作成された公正証書遺言については、日本公証人連合会が構築した遺言情報管理システムに情報が管理 されており、全国の公証役場で遺言書の有無や保管公証役場を検索することができます。この検索は無料で、秘密保持のため、相続人等の利害関係人のみが申し出ることができます。
- 専門家の助言: 公証人が遺言者の意思能力を確認し、法的に有効で、解釈の余地が生じにくい明確な内容の遺言書作成をサポートします。聴覚や言語に障害がある場合でも、筆談や通訳を通じて作成が可能です。
- 出張作成も可能: 遺言者が病気などで公証役場に出向けない場合、公証人が病院や自宅などに出張して遺言書を作成することもできます。
デメリット
- 費用がかかる: 法律で定められた手数料が必要になります。財産の価額に応じて手数料が決定され、財産額が多額になるほど手数料も高くなります。例えば、財産額100万円以下で5,000円、100万円超200万円以下で7,000円、200万円超500万円以下で11,000円、500万円超1,000万円以下で17,000円、1,000万円超3,000万円以下で23,000円などと定められています。財産を渡す人が複数いる場合は、受遺者一人ごとに手数料が加算されることがあります。
- 証人が必要: 遺言者以外に、公証人と2人以上の証人が立ち会う必要があります。未成年者、推定相続人(相続人になる予定の人)、受遺者、これらの人の配偶者や直系血族、公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および使用人は証人になれません。自分で証人を見つけられない場合は、公証役場で紹介してもらうことも可能ですが、その場合は謝礼が必要となるのが一般的です。
【参考】民法969条を抜粋と要約
(公正証書遺言)第九百六十九条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
(公正証書遺言の方式の特則)第九百六十九条の二 口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号の口授に代えなければならない。この場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。
2 前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第三号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
3 公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。
民法第969条(公正証書遺言の方式)の要点
この条文は、公正証書遺言を有効に作成するための一般的なルールを定めています。公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が関与して作成されるため、形式不備で無効になるリスクが極めて低く、紛失や改ざんの心配もほとんどありません。
1. 証人の立ち会い:2人以上の証人が遺言の作成に立ち会う必要があります。
2. 遺言者の口述:遺言をする人が、公証人に対して遺言の内容を口頭で伝えます。
3. 公証人の筆記と確認:公証人が遺言者の口述を正確に書き取り、その内容を遺言者と証人全員に読み聞かせ、または閲覧させます。
4. 承認、署名、押印:遺言者と証人は、筆記された内容が正確であることを確認し、それぞれ署名と押印をします。
◦ もし遺言者が病気などで署名できない場合でも、公証人がその理由を付記することで、署名の代わりにすることができます。公証人が代筆し、遺言者が押印することも可能です。
5. 公証人の完成証明:公証人が、これまでの手順が法律の定めに従って行われた旨を書き加え、署名と押印をして、公正証書遺言を完成させます。公正証書遺言の原本は公証役場に保管されるため、紛失や盗難、偽造や改ざんを防ぐことができます。また、遺言者の死後、家庭裁判所による検認手続きが不要であるため、相続手続きがスムーズに進みます。
民法第969条の2(公正証書遺言の方式の特則)の要点
この条文は、遺言者が話せない、または耳が聞こえない場合の特別な対応について定めています。
1. 話せない遺言者の場合:
◦ 遺言者は、公証人や証人の前で、通訳人を介して遺言の内容を伝えたり、自分で文字を書いて示したりすることで、通常の「口頭で伝える」方法の代わりにすることができます
◦ この場合、公証人は、通訳による申述や自書された内容を書き取ります。
2. 耳が聞こえない遺言者または証人の場合:
◦ 公証人は、書き取った遺言の内容を、通訳人を介して遺言者や証人に伝えたり、直接閲覧させたりすることで、通常の「読み聞かせ」の代わりにすることができます。
3. 公証人の付記:これらの特別な方式に従って公正証書を作成した場合、公証人はその旨を証書に付記する必要があります。これらの特則により、話すことや聞くことが困難な人でも、安心して法的に有効な公正証書遺言を作成できる仕組みが整えられています。
公証人役場と公証人について
公証人役場とは?
公証人役場とは、公証人役場とは、公証人が法律に基づいて公正証書の作成などを行う場所です。日本全国に約300ヶ所あり、遺言書作成以外にも、契約書や会社設立に関する定款の認証、金銭消費貸借契約などの債務名義となる公正証書の作成も行っています。
静岡県内の公証人役場
| 公証役場 | 郵便番号 | 所在地 | TEL | FAX |
|---|---|---|---|---|
| 静岡合同 | 420-0853 | 静岡市葵区追手町2-12 安藤ハザマビル3階 shizuoka-koshoyakuba@grace.ocn.ne.jp | 054-252-8988 | 054-251-0944 |
| 沼津合同 | 410-0801 | 沼津市大手町3-6-18 住友生命沼津ビル5階 numazu-koushou@rx.tnc.ne.jp | 055-962-5731 | 055-962-5766 |
| 熱海 | 413-0005 | 熱海市春日町2-9 熱海駅前第二ビル3階 atami-kousyouyakuba@olive.plala.or.jp | 0557-82-7770 | 0557-82-7788 |
| 富士 | 417-0055 | 富士市永田町1-124-2 EPO富士ビル2階 fuji-notary@tmt.ne.jp | 0545-51-4958 | 0545-51-4957 |
| 浜松合同 | 430-0946 | 浜松市中央区元城町219-21 第一ビル2階 kosyo@yn-hamamatsuyakuba.jp | 053-452-0718 | 053-452-4308 |
| 掛川 | 436-0056 | 掛川市中央2-4-27 中央ビル5階 kk-yakuba2427@tmt.ne.jp | 0537-22-2304 | 0537-22-2459 |
| 袋井 | 437-0023 | 袋井市高尾1129-1 袋井新産業会館キラット3階 fukuroi-kosho@muse.ocn.ne.jp | 0538-42-8412 | 0538-30-7587 |
| 下田 | 415-0036 | 下田市西本郷1-2-5 佐々木ビル3階 simoda-notary@cy.tnc.ne.jp | 0558-22-5521 | 0558-22-5521 |
| 焼津 | 421-0205 | 焼津市宗高900番地 焼津市役所大井川庁舎2階 yaizu-notary@iaa.itkeeper.ne.jp | 054-668-9933 | 054-668-9934 |
その他、公証役場の一覧はこちらから!
公証人ってどんな人?
公証人は、長年裁判官、検察官、または弁護士として実務経験を積んできた法律専門家 です。法務大臣によって任命され、複雑な法律知識と豊富な経験を持つため、遺言者の真意をくみ取り、法律的に正確な遺言書を作成することができます。
彼らは、遺言書が法的な効力を持つために必要な要件を熟知しており、遺言者が意図する内容が正確に反映されるよう助言します。
公証人の使命と公証業務について
公証人は、国家公務員法上の公務員ではありませんが、国の公務である公証作用を担う実質的な公務員です。
公証人が担う公証事務は、国民の権利義務に関係し、私的紛争の予防の実現を目指すものであり、公証人が作成する文書には、強制執行が可能である公正証書も含まれます。
そのため、公証人は、単に高度な法的知識と豊富な法律実務経験を有していることが必要であるばかりでなく、職務の性質上、一方当事者に偏ることなく、中立・公正でなければなりません。この点で、一方当事者からの依頼を受けて、依頼者の代理人等として依頼者の公正な利益のために活動する弁護士や司法書士等とは異なっています。
公証人は、原則として、裁判官や検察官あるいは弁護士として法律実務に携わった者で、公募に応じたものの中から、法務大臣が任命しています(公証人法第13条)。
また、多年法務事務に携わり法曹有資格者に準ずる学識経験を有する者で公募に応じ、かつ、検察官・公証人特別任用等審査会の選考を経たものについても、法務大臣が公証人に任命しています(公証人法第13条の2)。
公証人は、国の公務である公証作用を担う実質的な公務員ですが、国から給与や補助金など一切の金銭的給付を受けず、国が定めた手数料収入によって事務を運営しており、手数料制の公務員とも言われています。
公証人は、全国で約500名おり、公証人が執務する事務所である公証役場は約300箇所あります。
参考:日本公証人連合会HP「第1 公証人の使命と公証業務について 公証人とは」
公正証書遺言の作り方と費用
公正証書遺言を作成する場合、以下の流れで進められます。
1. 必要書類の準備
公証役場に持参、郵送、またはFAXで送る必要のある書類を準備します。
- 遺言者に関する情報:
- 遺言者の 印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内)、氏名、住所、生年月日、職業などをまとめたメモ。
- 本人確認のため、マイナンバーカード、運転免許証などの顔写真付き公的身分証明書の提示も求められます。
- 相続人・受遺者に関する情報:
- 相続人や受遺者(財産を受け取る人)の氏名、住所、生年月日、職業、そして遺言者との関係がわかる 戸籍謄本。
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本等)、相続人全員の戸籍謄本、住民票の写し などが必要になります。
- 財産に関する情報:
- 不動産: 登記事項証明書、固定資産税評価証明書など。(登記簿上の所在地、地番、家屋番号、構造、床面積などの情報)
- 預貯金: 金融機関名、支店名、口座番号がわかる通帳や証書のコピー。
- その他: 有価証券、借入金など。
2. 公証人役場への相談・依頼(事前相談料は無料!)
公正証書遺言の作成は、公証役場に直接電話で予約を取って相談することができます。この事前相談はすべて無料です。
公証人は、相談を通じて遺言者の意思や財産の状況などを確認し、遺言書の原案作成に必要な情報や書類について具体的なアドバイスをしてくれます。
公証人との相談をスムーズに進めるためにも、上記の情報はできるだけ集めておきましょう。
しかし、中には入手が難しい書類があったり、どうやって取得すればいいかわからないこともあるかもしれません。そんな時は一人で悩まず、専門家へ相談してみてください。
3. 遺言公正証書(案)の作成
公証人は、提出された書類と相談内容をもとに遺言書の原案を作成します。
遺言者は原案を確認し、修正が必要であれば公証人と相談しながら内容を確定させます。この段階で、遺言者の希望を法的に有効な形で表現するための調整が行われます。
4. 公正証書遺言の作成
最終案が確定したら、遺言者、公証人、そして2人以上の証人が公証役場に出向きます。遺言者が口頭で遺言内容を告げ、公証人がその内容を筆記し、間違いがないことを確認した上で署名・押印し、完成となります。
費用について
公正証書遺言の作成費用は、遺言の対象となる財産の総額によって決まります。財産額が多ければ多いほど、手数料も高くなります。
- 財産額100万円以下: 5,000円
- 財産額100万円超500万円以下: 11,000円
- 財産額500万円超1,000万円以下: 17,000円
- 財産額1,000万円超3,000万円以下: 23,000円
- 財産額3,000万円超5,000万円以下: 29,000円
上記に加え、財産を渡す人(相続人や受遺者)が複数いる場合は、1人増えるごとに手数料が加算されます。また、病院などに出張してもらう場合は、別途日当や交通費も必要になります。
専門家に依頼する場合
公正証書遺言の作成は、弁護士、司法書士、行政書士に依頼することも可能です。
- 弁護士:
- 家族間の複雑な問題や将来的な紛争が予想される場合、法的なトラブル解決の予防という観点から、弁護士への依頼が適しています。
- 遺言書の内容について、遺言者の真意が法的に適切に表現されているかを確認し、曖昧な文言による将来の争いを避けるための助言を得られます。
- 遺留分など、他の相続人の権利を侵害する可能性のある内容を検討する際にも、適切なアドバイスが期待できます
- 司法書士:
- 不動産の相続登記手続きをスムーズに進めたい場合や、正確な不動産の表記が必要な場合に強みを発揮します。
- 法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用する際の申請書作成などを依頼することも可能です。
- 遺言書作成のノウハウを持っており、非の打ちどころがない遺言書を作成するためのサポートが期待できます
- 行政書士:
- 行政書士も公正証書遺言の作成を行うことができます。相続開始後の相続人の負担を減らすための準備もサポートします。
- 遺言執行者の業務についても知見があり、死後事務委任などの提案も可能です。
多くの事務所が初回無料相談を行っていますので、まずは気軽に問い合わせてみてください。
相続は個々の事情が複雑に絡み合うため、専門家の知識だけでなく、親身に話を聞いてくれる、あなたにぴったりのパートナーを見つけることが何より大切です。
行政書士業務の範囲を超える場合は、必要に応じて弁護士や司法書士、税理士などの専門家につなぐことも可能ですので、安心してご相談ください。