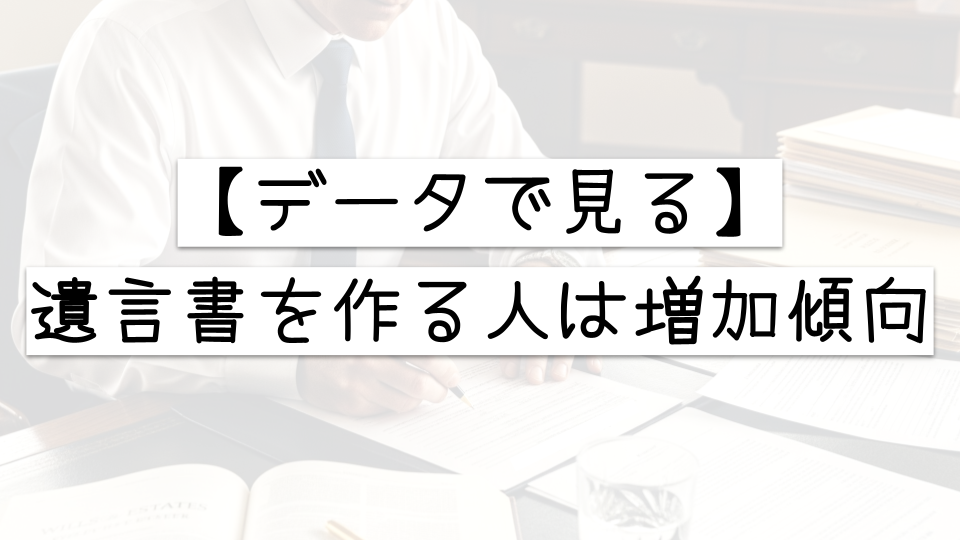近年、遺言書を作成する件数は増えています。
遺言書の作成方式は、主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2つが代表的です。2020年7月から法務局で遺言書を保管する「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。
| 項目 | 自筆証書遺言 | 自筆証書遺言(保管制度) | 公正証書遺言 |
|---|---|---|---|
| 費用 | 無料(筆記具や用紙代を除く) | 保管申請に3,900円(他費用あり) | 遺産額などに応じた公証人手数料 |
| 作成方法 | 遺言者本人(15歳以上)が全文、日付、氏名を自筆で書く(財産目録はPC可) | 自筆証書遺言を作成後、法務局に保管を申請 | 2人の証人の前で口頭で公証人に伝える |
| 証人の有無 | 不要 | 不要 | 2人必要(公証役場で紹介可能) |
| 保管場所 | 自宅など遺言者自身が保管 | 法務局 | 原本は公証役場正本・謄本は遺言者本人が保管 |
| 紛失・偽造リスク | あり(紛失、改ざん、隠匿のリスクがある) | ほぼない(法務局が原本を保管) | ほぼない(公証役場が原本を保管) |
| 死亡時の通知制度 | なし | あり | なし |
| 検認の要否 | 家庭裁判所での検認が必要 | 検認は不要 | 検認は不要 |
上記で紹介した方式以外にも、「秘密証書遺言」や、病気などで死が差し迫った状況で利用できる「特別方式の遺言」があります。しかし、一般的に広く活用されている方式ではありませんので、今回の記事のご紹介からは除いています。
そもそも日本で遺言書をどれくらい準備している?
日本財団の調査によると、60歳~79歳で遺言書をすでに作成している人は3.4%(公正証書遺言書1.7%、自筆証書遺言書1.7%)にとどまり、近いうちに作成予定は12.2%でした。
「しばらく作成するつもりはない」は34.1%、「今後も作成しない」は45.9%と、作成予定や意向が無い人は8割という結果です
遺言書準備状況
<日本財団「遺言・遺贈 に関する意識・実態把握調査 要約版」/2025年 3月31日より抜粋掲載>
本調査はインターネット調査であり、回答数も2,000件ということで、どこまで実態をとらえているかは検討する必要はありますが、「遺言書をすでに作成している人は3.4%」このデータだけ見ると、遺言書作成の件数はまだまだ日本全体でみると少ない印象です。
遺言書を作る人は少しずつ増えている
しかし、法務局や家庭裁判所などにデータを見ると、遺言書作成の件数が徐々に増えてきていることが伺えます。
自筆証書遺言も徐々に増えている?
自分で作成し保管できる自筆証書遺言は、年間でどれくらいの件数が作られているのか正確に知ることはできません。ただ、関心の高まりを示す2つの重要なデータがあります。
1. 法務局に保管される遺言書の数
2020年から始まった「自筆証書遺言書保管制度」は、遺言書を法務局に預けることで、紛失や改ざんのリスクを防ぎ、検認手続きも不要になります。
この制度の利用件数は年々増えており、法務省民事局が発表しているデータは以下の通りです。
2020年:12,631件
2021年:17,002件
2022年:16,802件
2023年:19,336件
2024年:23,419件
大切な遺言書を安全に保管したいと考える方が増えていることがわかります。
参考:法務省「自筆証書遺言書保管制度」サイト内「12 法令・関連情報・リンク集」に掲載されている「利用状況(令和7年6月)」
2. 家庭裁判所での検認件数
もう一つの重要なデータは、家庭裁判所における遺言書の検認件数です。これは遺言者が亡くなった後に手続きされるものですが、遺言書に対する関心の高まりを測る良い指標となります。
司法統計年報(家事編)によると、検認件数は長期的に増加傾向にあり、特に近年は顕著な伸びが見られます。
1949年:367件
1975年:1,870件
2005年:13,083件
2015年:19,808件
2020年:21,782件
2022年:22,802件
2024年:23,436件
これらのデータは、遺言書に対する社会全体の関心が高まり、実際に作成する方が増えていることの表れだと感じます。
参考:最高裁判所事務総局「令和6年 司法統計年報(民事・行政編)」
公正証書遺言の作成件数も少しずつ増えており、2024年は直近10年で最も多いです件数でした
公正証書遺言は、公証人が関与して作成するため、日本公証人連合会が毎年作成件数を公表しています。このデータから、公正証書遺言の作成件数がどのように変化しているかを見てみましょう。
<公正証書遺言の年間作成件数>
2015年:110,778件
2016年:105,350件
2017年:110,191件
2018年:110,471件
2019年:113,137件
2020年:97,700件
2021年:106,028件
2022年:111,977件
2023年:118,981件
2024年:128,378件
近年は作成件数が年々増加しており、遺言書に対する関心の高まりがうかがえます。特に、最新の2024年の数字は過去10年間で最も多くなっています。
参考:日本公証人連合会「令和6年の遺言公正証書の作成件数について」
遺言書の種類とそれぞれの特徴(メリット・デメリット、手続き)
ここまでで、実際に作成する方が増えていることを見てきました。
遺言書を書く人が増えているとは言っても、それぞれどんな特徴があるのでしょうか?
ここからは、ご自身の状況に合った遺言書を見つけるために、3つの代表的な方式(自筆証書遺言、自筆証書遺言保管制度、公正証書遺言)について、それぞれの特徴やメリット・デメリットを分かりやすく解説します。
1. 自筆証書遺言
遺言者自身が、手書きで作成する最も手軽な遺言書です。紙とペンがあればいつでも作成できる反面、法律で定められたルールを守らなければ無効になってしまうリスクもあります。
自筆証書遺言の概要
遺言者本人が、全文、日付、氏名をすべて自筆で書き、押印することで作成します。財産目録についてはパソコンで作成したものを添付することも可能ですが、各ページに署名と押印が必要です。この遺言書は、亡くなった後に家庭裁判所での「検認手続き」が原則として必要となります。
メリットとデメリット
- メリット
- 手軽さ:紙と筆記用具があればいつでも作成できます。
- 費用がかからない:公証役場の手数料や証人への謝礼が不要です。
- 秘密を守れる:ひとりで作成するため、内容を他人に知られることがありません。
- デメリット
- 無効になるリスク:法律で定められた要件(全文自筆、日付、氏名、押印など)を満たさないと、無効になる可能性が高いです。
- 紛失・改ざんのリスク:自分で保管するため、遺言者が亡くなった後に発見できなかったり、内容を改ざん、隠されたりなどする恐れもあります
- 検認の手間:亡くなった後、相続人が家庭裁判所で検認手続きを行う必要があり、負担となる場合があります。また、封印がされている遺言書を勝手に開封すると過料が科される可能性があります。
作成から手続きまでの流れ
- 作成:遺言者本人が、全文、日付、氏名を自筆で書き、押印します。
- 保管:作成した遺言書を、遺言者自身が大切に保管します。
- 検認(死亡後):遺言者の死亡後、発見者は家庭裁判所に提出し、検認を受けます。封印のある遺言書は、家庭裁判所の検認の場で開封しなければなりません。
2. 自筆証書遺言(保管制度)
自筆証書遺言の安全性を高めるために、2020年に始まったのがこの保管制度です。自筆で作成した遺言書を法務局に預けることで、紛失や偽造のリスクをなくすことができます。
自筆証書遺言(保管制度)の概要
自分で作成した自筆証書遺言を、公的機関である法務局で保管してもらう制度です。この制度を利用すると、遺言者が亡くなった後、遺言書が保管されている旨が関係相続人等に通知され、家庭裁判所での検認手続きも不要となります。
メリットとデメリット
- メリット
- 安全性が高い:法務局が遺言書の原本を保管するため、紛失、盗難、偽造、改ざんのリスクを大幅に防ぐことができます。
- 検認が不要:相続人にとって負担となる家庭裁判所での検認手続きが不要です。
- 発見が容易:遺言者の死亡後、あらかじめ指定された人に遺言書が保管されている旨の通知が届きます。また、関係相続人等の誰かが遺言書の閲覧や情報証明書の交付請求をすると、他の全ての関係相続人等にも通知が届くため、遺言書の存在が伝わります。
- 全国対応:モニターによる遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付請求は、全国どこの法務局でも手続きが可能です。
- デメリット
- 費用がかかる:保管の申請に手数料(3,900円)がかかります。また、閲覧や情報証明書の交付にも別途手数料が必要です。
- 様式の制限:法務省令で定められた特定の様式で作成する必要があります。
- 本人出頭義務:保管を申請する際、遺言者本人が直接法務局に出向く必要があります。
- 内容の相談はできない:法務局では遺言書の形式的なチェックはしてくれますが、内容に関する相談はできません。
手続きの流れ
- 遺言書の作成 まず、民法のルールに沿って、ご自身で遺言書を作成します。この際、封筒には入れず、無封の状態で作成します。
- 法務局での申請を予約 遺言書を保管してもらう法務局を選び、事前に予約します。申請できる法務局は、遺言者本人の住所地や本籍地、または所有する不動産の所在地を管轄している法務局です。
- 法務局での手続き 予約した日時に、遺言者本人が法務局に出向いて手続きを行います。このとき、以下のものを持参しましょう。
- 作成した遺言書の原本
- 記入済みの申請書
- 手数料(3,900円の収入印紙)
- 顔写真付きの身分証明書(運転免許証など)
- 住民票の写し(本籍と筆頭者記載、マイナンバーなしのもの)
申請時に希望すれば、遺言者本人に万が一のことがあった場合、法務局から遺言書が保管されていることを知らせてほしい人(通知対象者)を最大3名まで指定できます。
- 保管証の交付 法務局が遺言書の保管を始めると、その証明として保管証が交付されます。
- 預けた遺言書を閲覧:生前に自分の遺言書の内容を確認したい場合、遺言者本人のみが閲覧請求できます。閲覧には、遺言書の原本を見る方法と、モニターで画像を見る方法があります。原本閲覧は、遺言書を保管している法務局でしかできませんが、モニター閲覧は全国どの法務局でも可能です。
- 変更や撤回 遺言書の内容を変更したい場合は、いつでも新たな遺言書を作成し、再度保管を申請できます。すでに保管してある遺言書を撤回することも可能です。
- 遺言書情報の確認(死亡後) あなたの死後、相続人などが法務局に請求することで、遺言書が保管されているかどうかを確認したり、内容を閲覧したりできます。この手続きを誰か一人が行うと、他の相続人全員にも自動的に通知が届く仕組みになっています。
3. 公正証書遺言
公証人が関与して作成するため、効力が無効になる可能性は低い遺言書です。作成に当たっては、事前に遺言書の文章案を公証人と打合せや資料作成などを行います。病気などの理由により、口頭での話が難しい人や耳が聞こえない人には通訳などの対応も可能です。
公正証書遺言の概要
公証人が、遺言者から口頭で聞いた内容を筆記し、証人2名とともに署名・押印して作成します。原本は公証役場に保管され、相続時の検認手続きは不要です。
メリットとデメリット
- メリット
- 無効になるリスクが極めて低い:法律の専門家である公証人が作成するため、形式不備で無効になる心配がほとんどありません。
- 紛失・偽造・改ざんの心配がない:原本が公証役場に永久保管されます。
- 身体的な制約への対応: 病気などで字が書けない、署名・押印が困難な場合でも、公証人が代筆したり、署名・押印を代行したりすることが法律で認められています。また、口がきけない人や耳が聞こえない人でも、筆談や手話通訳、または閲覧により遺言書を作成できます。
- 出張対応: 遺言者が高齢や病気で公証役場へ出向けない場合、公証人が遺言者の自宅や病院などに出張して遺言書を作成することが可能です。
- 検認が不要:家庭裁判所での検認手続きが不要なため、相続手続きがスムーズに進みます。
- デメリット
- 費用がかかる:公証人への手数料や、証人への謝礼が必要です。財産の価額に応じて手数料は異なります。
- 証人が必要:証人2名を自分で手配するか、公証役場に紹介してもらう必要があります。
公証人手数料(参考)
契約やその他の法律行為に係る証書作成の手数料は、原則として、その目的の価額により定められています(手数料令9条)。目的の価額というのは、その行為によって得られる一方の利益(相手からみれば、その行為により負担する不利益ないし義務)を金銭で評価したものです。
目的の価額は、公証人が証書の作成に着手した時を基準として算定します。
【法律行為に係る証書作成の手数料】(公証人手数料令第9条別表)
| 目的の価格 | 手数料 |
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円超〜200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円超〜500万円以下 | 11,000円 |
| 500万円超〜1,000万円以下 | 17,000円 |
| 1,000万円超〜3,000万円以下 | 23,000円 |
| 3,000万円超〜5,000万円以下 | 29,000円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 43,000円 |
| 1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
| 3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
| 10億円を超える場合 | 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
贈与契約のように、当事者の一方だけが義務を負う場合は、その価額が目的の価額になりますが、売買契約のように、売主と買主の双方が義務を負う場合は、双方が負担する価額の合計額が目的の価額となります。
数個の法律行為が1通の証書に記載されている場合には、それぞれの法律行為ごとに、別々に手数料を計算し、その合計額がその証書の手数料になります。法律行為に主従の関係があるとき、例えば、金銭の貸借契約とその保証契約が同一証書に記載されるときは、従たる法律行為である保証契約は、計算の対象には含まれません(手数料令23条)。
任意後見契約のように、目的の価額を算定することができないときは、例外的な場合を除いて、500万円とみなされます(手数料令16条)。
以上のほかに、証書の枚数による手数料の加算があります(手数料令25条)。
手続きの流れ
- 公証人との事前相談: 遺言内容について公証役場の公証人と打ち合わせを行います。この段階で遺言公正証書の案を作成します。
- 必要書類の準備: 遺言者本人の印鑑登録証明書(3か月以内に発行されたもの)、相続人との続柄を示す戸籍謄本、遺贈を受ける人(相続人以外)の住民票、不動産を相続させる場合はその登記事項証明書や固定資産評価証明書、預貯金の場合は預貯金通帳のコピーなど、財産の内容に応じた書類を準備します。
- 証人の準備: 証人2名(欠格事由に該当しない成人)を用意します。自身で手配できない場合は、公証役場に紹介を依頼することも可能です。
- 作成日時の確定: 公証人と遺言者(および証人)の間で、公証役場での面談または公証人の出張による遺言書作成の具体的な日時を決定します。
- 遺言日当日の手続き:
- 遺言者本人が、公証人に対し、証人2名の前で遺言の内容を口頭で告げます。
- 公証人は、それが遺言者の真意であることを確認し、事前に準備した公正証書の原本を遺言者と証人2名に読み聞かせるか、閲覧させ、内容に間違いがないことを確認してもらいます(必要に応じて修正)。
- 内容に間違いがなければ、遺言者と証人2名が原本に署名し、押印します。遺言者が署名や押印できない場合は、公証人がその旨を記載し、職印を押捺することで代えることが認められています。
- 最後に公証人も署名し、職印を押捺して公正証書遺言が完成します。
- 遺言者が真意を述べられるよう、利害関係者(相続人など)は当日は席を外す運用がされています。
- 正本・謄本の交付: 完成した公正証書遺言の正本1通と謄本1通が遺言者に交付されます。
まとめ
どの遺言書も、大切なご家族にあなたの想いを伝えるための重要な手段です。
- 手軽さを重視するなら「自筆証書遺言」
- 安全かつ手間なく遺言を残すなら「自筆証書遺言(保管制度)」
- 確実性やトラブル防止を最優先するなら「公正証書遺言」
これらのメリット・デメリットを比較し、ご自身の状況や目的に合ったものを選ぶことが大切です。
遺言書の内容は複雑なケースも少なくありません。
もしご自身での判断が難しいと感じたら、専門家に相談することで、より安心して遺言書を作成できます。
初回の無料相談を利用して、まずはご自身の状況を専門家に話してみることから始めてみてはいかがでしょうか。